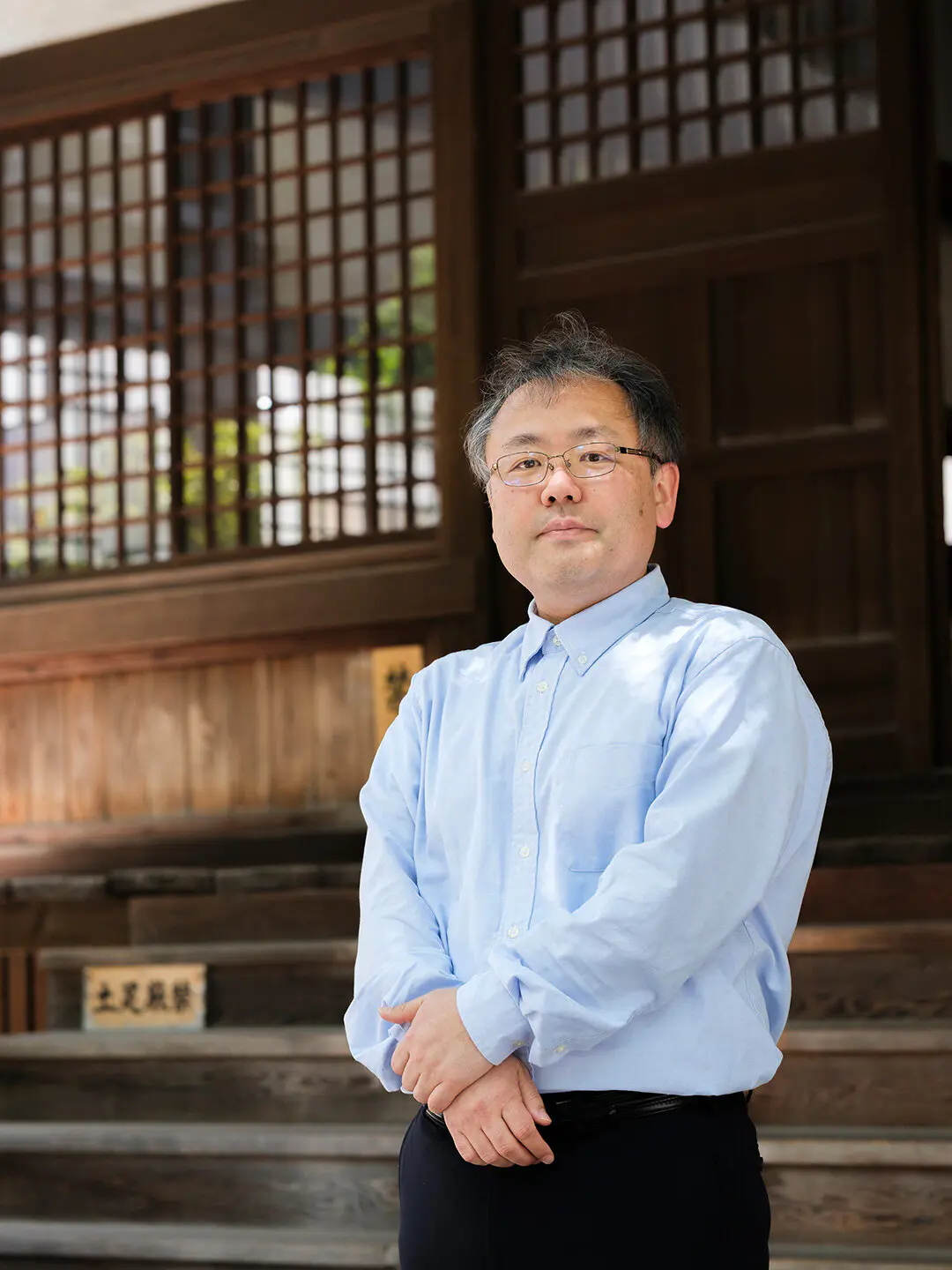
国士舘を語る。
- タイパに挑んだ編集講義 -
2024年度から全学共通教育の目玉科目としてスタートした秋期開講科目「国士舘を語る - 継承する精神文化の探究 - 」。実はこの講義、7名の教員たちが合議制で作り上げています。大河ドラマ的とも称される人気講義の秘密に迫ります。国士舘を語ろう

「国士舘を語る」。これは、2024年度より始まった全学共通教育のコアカテゴリー「国士舘を学ぶ」に位置付けられている科目です。創立者である柴田德次郎がなぜ国士舘を作ったのか、その時代背景を、社会情勢、歴史、地政学、文学、経済学など多彩な視点を通じて、どのような出来事や人物が有機的に絡み合っていたのかを全15回の講義を通して紐解いていきます。特に大きな影響を与えた、吉田松陰にも大胆に迫ります。
コアカテゴリー「国士舘を学ぶ」には、春期の1年生必修科目として、国士舘の建学の精神や教育理念を学ぶ「国士舘を知る」があります。こちらはオンデマンド動画で講義を視聴します。1学年3000人近くおり、対面講義が難しいためにこの形式となりました。その後、秋から始まる講義である「国士舘を語る」を受講したい学生を募集します。こちらは対面での授業です。2024年度は想定していた160名を超えて、290名の応募があり最終的に190名に絞りました。本当はすべての学生を受け入れたいのですが、最も大きな教室でも対応できない人数であったため、泣く泣く絞らざるを得ませんでした。
秋講義のタイトルを「語る」としたのは、ただ歴史を辿ることをするのではなく、文字通り、知識知見を持った人間が多様な視点で国士舘という存在をあぶり出していく内容であることを示唆したつもりです。歴史的出来事の周辺には無数の出来事が存在しており、その様相は極めて複雑です。どの角度、どの人物から見るかでも、多様な捉え方が可能です。また、現代に生きる我々の状況によっても、過去の捉え方が変化します。今も昔も、大学を創設するのは生半可なことではありません。広大な土地が必要であるということもありますし、教育機関として国の認可を受けるために、膨大な資金や人材、人脈が必要不可決です。さまざまな知識人や財界の協力者の存在も絡みます。当然そこには、当時の社会に育まれていた主義主張や政治、経済といった状況が織りなす素晴らしい景色が広がっています。「国士舘を語る」ということは、当時の社会を取り巻く様々な人物から事象にいたるまでを立体的に捉え理解することなのです。
7人の語り部

当授業は7名の教員による合議制によって作られています。雑誌やTVのコンテンツを作る編集会議のようなスタイルだと言えばわかりやすいかもしれません。誰が学生に対してどのような講義を展開するかを、月1回ぐらいの研究会で共有しながら、学生に対して響く内容は何かを徹底的に議論しています。「楽しい授業を目指そう」を合言葉に、準備に1年半近くを費やしました。たとえば試験に関しても、毎授業終わりに小テストをやって、期末の試験は行わないようにし、学生が参加する意欲が継続できるよう配慮しています。授業中にクイズを出しながら、雑学的面白さを体験できるように工夫を凝らしていることもその一環です。教員ごとに専門が異なるため、多様な視点によるディスカッションは本当に面白く、講義の質を高めています。学生にわかりやすくも丁寧に本質を伝えることに極めて有益だということは、我々が身をもって体験しているところです。普段の講義内容を作成するのは、基本教員一人で行うためこのように多様な視点は入りません。今回の講義内容作成は面白くて仕方ありません。
全体を通しての、内容のバランスには最新の注意を払っています。創立者の柴田德次郎は、吉田松陰に大きな影響を受けるわけですが、そもそもほとんどの学生は吉田松陰をよく知りません。とはいえ、吉田松陰寄りの内容にしたら国士舘創立というフォーカスがボケてしまいます。全15回の授業の中で、吉田松陰は3回ぐらい。そして、柴田德次郎が松陰にどのように影響を受け、松陰神社の隣地を大学の地としたのかというような話が少々。さらに、国士舘が目指した教育と吉田松陰がどのようにつながっているのかまでを合わせて、全体の半分くらいにとどめています。重要なのは、当時をより深く理解するために日本の伝統文化や精神文化を学ぶことだと考えています。それこそ古事記から始まり、神道、武士道、仏教をはじめとする、日本の思想の基礎について解説しています。

そもそも、四季が巡ってきて自然と農作物を収穫できる日本人の宗教観や世界観と、どんどん荒れ地を開拓し採掘して狩猟するという西洋のアグレッシブな生活から育まれた文化は全く異なるものです。当然、資本主義や民主主義、さらには科学に対する捉え方も異なったものとなります。ここを理解できなければ、吉田松陰、柴田德次郎といった人々が生きている時代に感じていた、当時の社会の変化や危機意識などが不明瞭となり、時代を読み解くことができなくなってしまうので、我々も細心の注意を払いながら授業を構築し、内容を吟味しています。
学生からの高評価

2024年度の授業を受けた学生にアンケートを実施した結果、評価が大変ポジティブであり、我々にとって大いに励みになりました。小テストの回答率が高く、授業の感想についても多くの学生が記述してくれました。実はこの講義にはもうひとつ重要なテーマが設定されています。それが「タイパへの挑戦」です。現代ではよく使われるようになった言葉であり、費やした時間に対する効果や満足度を指します。しかし一方で、物事をじっくり深く理解することが軽んじられる傾向も強くなっているように感じられる中、タイパの価値について講義を通して追求していこうと考えました。
改めて国士舘の設立趣意書を読み返してみると、当時、柴田らが感じていた危機意識というのは、社会全体がとかく稚拙にヨーロッパの真似をしようとすることに対する警鐘にあることがわかります。うわべだけで西洋知をもてはやし、導入し推進させようとすることに対する批判が記述されています。どうでしょう、タイパが普及することで、物事を表面的にしか捉えられない人材が増えることに対する現代の懸念と類似しているように感じませんか?国士舘の教育理念には、「誠意・勤労・見識・気魄」があり、これらが日本の将来を担う「国士」に必要であると説かれています。歴史的に日本人というのは、他者との調和を重視する人間関係の中でより良い社会構築を実践してきました。西洋の自己主義とか功利主義という、自分が頑張ってお金を儲ければ良い、人を蹴落としても良いから利益を追求するといった考え方は、そのままでは日本の文化を壊してしまう。だからこそ柴田らは、国士舘創立を通して日本文化を継承する国士を生み出さねばならないと考えたわけです。こうした状況を学生が現代感覚で理解することができれば、理解や興味を活性化することができます。タイパという概念を活用できたことは、ある意味幸運な発見でした。
実践へつながる道へ
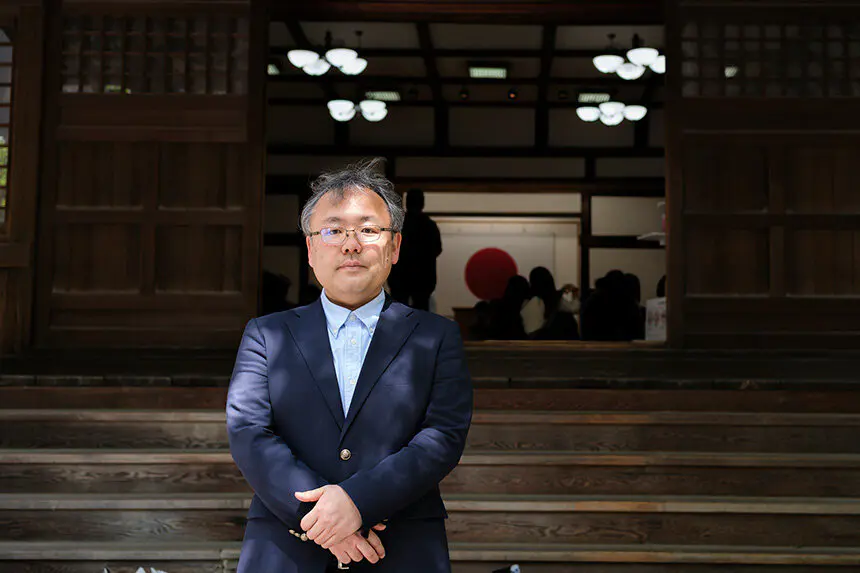
吉田松陰は1859年に29歳という若さで亡くなっています。幕末の日本に多大な影響を与えた側面がフォーカスされがちですが、当然一般の生活者として我々と同じ悩みを持っていました。たとえば、弟子には、生活をしっかりさせてからその上で国のことを考えなければダメだと説いていたりと、現実的な側面もあります。一方、ペリーの黒船が来た時に日本人が右往左往してどうしていいかわからない時、単身で黒船に乗り込んで渡米の交渉をするというとんでもないことをやってのけている。ペリーも、すごい奴がいる国、日本は侮れないぞ、この国はいずれ台頭してくると記録しているほどです。その後、黒船乗船が原因で幕府に捕まった吉田松陰が監獄にいる間に、牢獄内で勉強会をしたエピソードや、牢獄内に豊かな差し入れがあったりといった逸話にも事欠かない。こうした松陰の話を聞き、学生の中には松陰神社に足を運んでくれた学生もいたようで、講義の成果の一つとして嬉しく捉えています。
2025年度秋の講義も、その後もこの講義は続きます。今年も応募が多く嬉しい悲鳴が続いていますが、対面でやることには強い手応えを感じており、継続していきます。より多くの学生との対面授業ができるよう調整したり、より充実した講義内容にすべくチームで議論を深めているところです。国士舘創立、というポイントを変えないということは大変重要であり、かつ大きな意義があります。人物の視点を変えたり、別の出来事から捉えたりするなど、切り口もまだまだたくさんあります。2024年度の内容を継承しながら、よりユニークなエッセンスを加え続けていくことができるため、毎年新しい発見を学生のみなさんにお届けできることでしょう。1本の大河ドラマを見に来てるような体験価値を感じていただけるととても嬉しく思います。学問というのは、”目を開く”ことができるものです。国士舘創立の事実を通して、柴田德次郎や吉田松陰が言わんとしているところが少しでも見えるようになれば、実際の生活でも意識が変化していくはずです。そうやって生まれる行動=実践を促すことに我々の講義が寄与できれば最高です。
話を聞いた先生
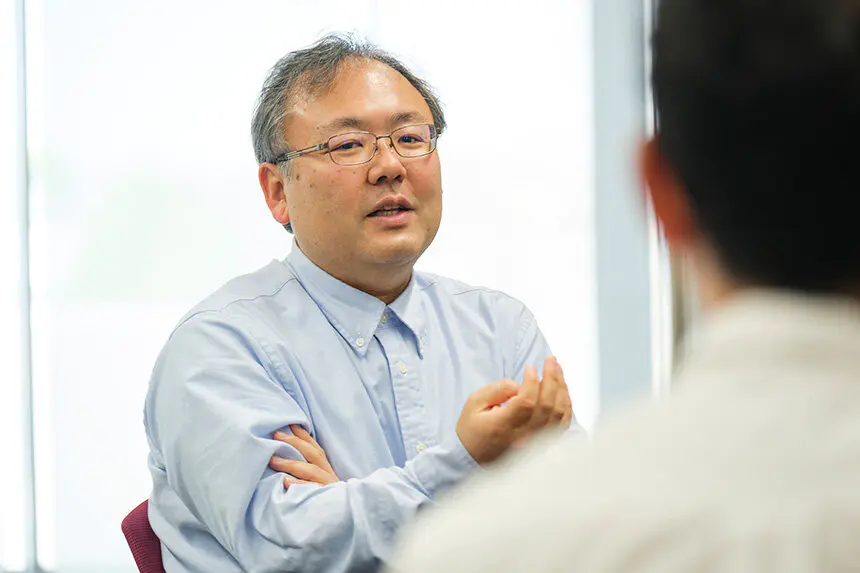
松野 敏之 国士舘大学 文学部教授
2001年に國學院大學 文学部 中国文学科 卒業。2004年早稲田大学大学院 文学研究科 東洋哲学専攻修士課程修了、2009年同博士課程単位取得、満期退学。2005年〜2007年には北京大学に留学。2010年 博士(文学)(中国哲学)(早稲田大学)。さまざまな大学での非常勤講師、研究員を務めた後、2020年より国士舘大学 文学部 文学科 教授を務める。





