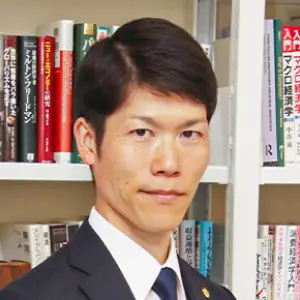3+1ゼミ合同SDGsプロジェクトでは、食品ロス対策の“秘密”を聞き出すため、基礎ゼミナールの学生たちが多種多様な団体にインタビュー調査を実施しています。6月中旬には赤石ゼミが、東京都目黒区・世田谷区・八王子市・町田市の担当者の方々に個別にインタビューを行いました。
本調査では、学生16名が4名ずつのチームに分かれ、事前勉強会では①取り組みの背景、②成功事例と秘訣、③直面する課題と要因、④今後の方向性と連携可能性──の四つの視点から質問項目を設計しました。インタビュー当日は、信頼関係の構築を重視した自己紹介から始め、現場ならではの工夫や苦労、次のステップに向けた想いまで、多角的にお話を伺いました。
主な気づき(概要)
・広報・周知活動の工夫が、住民の気づきと参加を促す大きな原動力となっている
・地方自治体と地域企業・団体との連携が、持続可能な仕組みづくりに寄与している
・限られた予算や人員の中でも、継続的な取り組みを支える工夫が随所に見られる
・計画の見直しやデータ活用を通じて、成果を確実に評価・改善しようとする姿勢が印象的
続く6月下旬には柴田ゼミが世田谷区社会福祉協議会とオンラインでインタビューを実施しました。毎年、大学祭期間に実施するフードドライブで回収した余剰食料品の受け入れ先として、地域の福祉を担う団体としてお世話になっています。事前勉強会では、社会福祉協議会の①食品ロス対策の特徴、②成功事例とその秘訣、③現在の課題とその要因、④今後の方向性と他団体との連携の可能性について、質問内容をグループ内で検討しました。インタビューを通じて、食糧支援を通じた活動が地域福祉につながることを学び得ました。
主な気づき(概要)
・食品ロスという目標に向けた多様な手段があることを理解できた。
・当初予定していた質問に対する回答から派生させて、急遽質問を投げかけることができた。
・市民の意識向上や制度の見直しなど、課題は山積している。
・AIの活用や需要予測などで効率的に活動はできないだろうか。
これらのインタビューを通じて、学生たちはテキストや動画だけでは得られない“生の声”を体感し、課題解決に向けた多角的な視点を身につけました。
最後に、本調査にご協力いただいた各自治体や世田谷区社会福祉協議会の担当者の方々に心より御礼申し上げます。秋期のアウトプット期間では、今回の知見をもとにして、新しい食品ロス対策を提案するための様々な企画を考えております。引き続き、皆さまのご支援・ご助言を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。