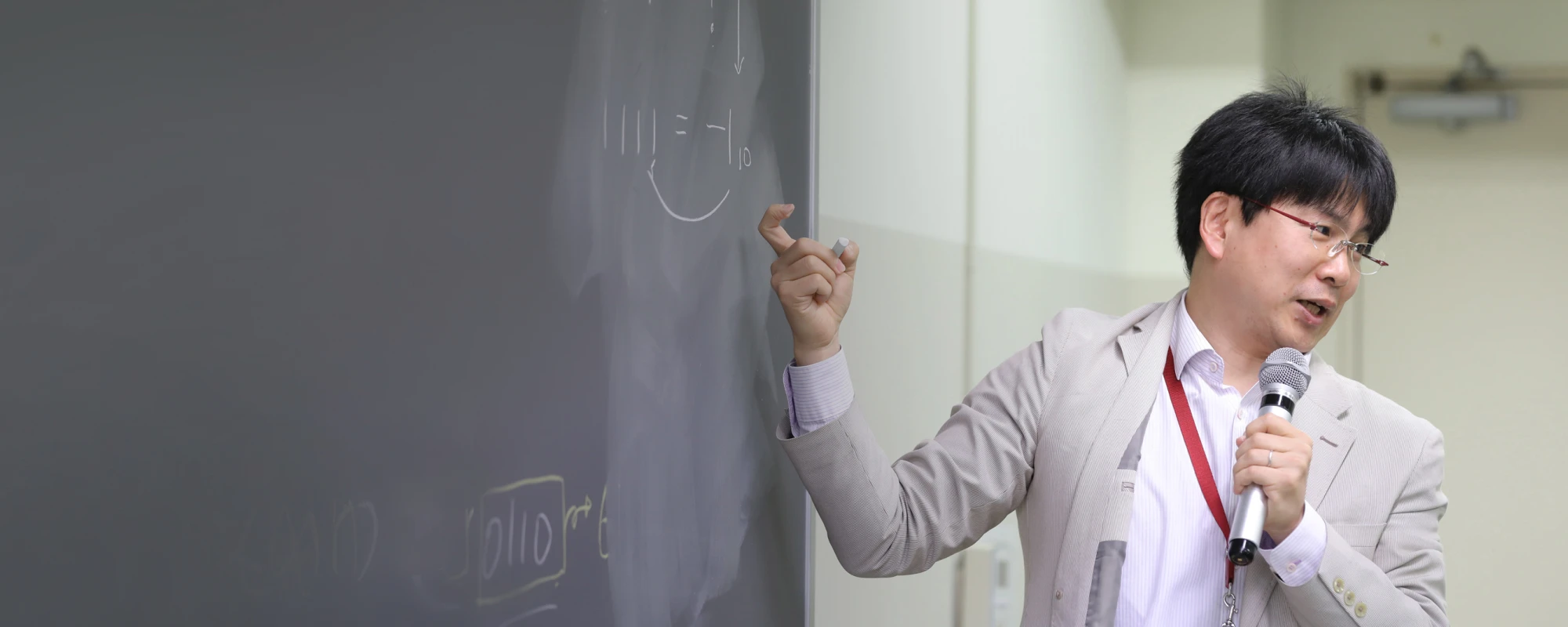Feature 学びの特色
-
01 地域の将来を担えるまちづくりの専門家の育成
「高い防災力と、地域の魅力を兼ね備えたまち」を大きなテーマに、「防災・減災まちづくり」、「都市デザイン」、「公共空間デザイン」、「土木構造と維持管理」、「河川環境」、「交通まちづくり」など、まちづくりの重要な技術を少人数制でかつ実践的に学びます。
-
02 実践的な知識や技術を身に付ける
講義や演習、研究室での研究活動や実践活動を通して、防災・減災技術による安全・安心のまちづくり、公共空間デザインによる都市再生、道路空間再編による賑わい創出、インフラの維持管理技術など、まちづくりの実践的な知識や技術を身に付けます。
-
03 充実のフィールド演習、設計コンペにも積極参加
実際のまちづくりの事例にふれるフィールド演習、具体的な場所のデザイン設計演習をはじめとする演習が豊富。設計コンペティションにも積極的に参加し、頭だけではなく、自ら考え、手を動かしながら、まちの課題を解決できる実践力を身に付けます。
まちづくり学ってなに?

都市や地域の計画やデザイン、街路や水辺、駅前広場といった公共空間のデザイン、橋梁や河川堤防といった土木施設の計画・設計・施工・維持管理など、住む人々が安全・安心で生き生きと暮らせる「まち」をつくるための学問です。
何を学ぶの?

図面の作成方法やスケッチ・模型などのデザイン表現の基礎、都市や公共空間のデザイン手法、構造物の設計技術や維持管理手法、地震や洪水などの自然災害を防ぐ技術など、これからのまちづくりに必要なデザインとエンジニアリングを学びます。
どんな将来が待っている?

まちの将来構想から運営を担う公務員、鉄道や高速道路などの事業者、公共空間や土木構造物の調査・計画・設計を担う建設コンサルタント、実際の工事を担う建設会社、エリアマネジメントを担うまちづくり会社などで活躍できます。


FIELD 分野紹介
-
防災・減災まちづくり分野
洪水による水害、地震による地滑りなど、自然災害の被害を抑えるハードやソフトの技術を学びます。高い防災力と、魅力ある地域づくりを両立する防災まちづくりの技術を身につけます。
-
地域・都市デザイン分野
人が主役のまちを実現する計画・設計技術と空間デザインを学びます。実際の都市を対象とした設計演習やフィールド演習を通じ、実践的なデザイン力を身につけます。
-
構造物設計・維持管理分野
橋や道路といった社会基盤施設の設計技術と維持管理技術について学びます。構造実験やフィールド調査、設計演習を通じ、地域に長く愛される構造物の設計力を身につけます。
Curriculum カリキュラム ― 4年間の学び
-

1年次
大学理数系の基礎知識を学びます。
-

2年次
基礎的な専門知識を学びます。
-

3年次
高度な専門知識を学びます。
-
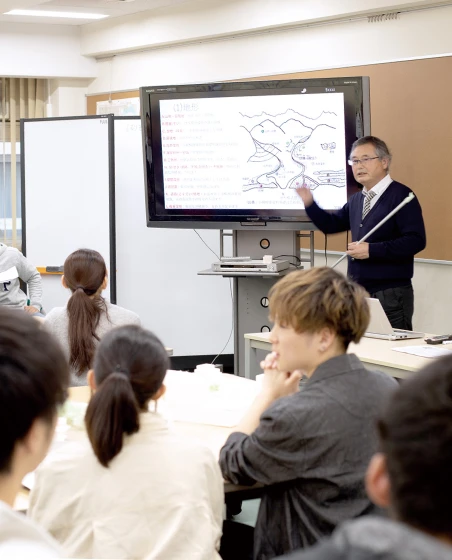
4年次
専門科目の学びを深めるとともに、学生生活の集大成である卒業研究にも取り組みます。
License 資格・免許
取得可能な資格・免許
まちづくり分野資格
技術士*、技術士補、測量士*、測量士補、1級・2級土木施工管理技士*、ランドスケープアーキテクト(RLA)*、1級・2級造園施工管理技士*、コンクリート技士*、地盤品質判定士*、地盤品質判定士補、土地家屋調査士、1級土地区画整理士*、特別上級*・上級*・1級*・2級*土木技術者*、防災士 など
*は、卒業後に資格ごとに定められた実務経験を経て受験資格が得られます。
教員免許状(一種)
| 高等学校一種 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 工業/(数学/理科/情報)※1 | (数学/理科/技術)※1 | - | - | - |
目指せる主な資格
技術士*、技術士補、測量士*、測量士補、土木施工管理技士*、ランドスケープアーキテクト(RLA)*、造園施工管理技士*、コンクリート技士*、土地家屋調査士、土地区画整理士*など
*は、卒業後に資格ごとに定められた実務経験を経て受験資格が得られる