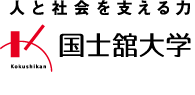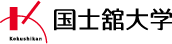テル・ジガーンC区の発掘
テル・ジガーンC区の発掘エスキ・モースル・ダム水没地域のなかでは、最大規模を誇る遺丘をもつ遺跡である。ティグリス河に接して存在する遺丘自体の面積は15ヘクタール近くあり、その裾野を含む遺跡全体の面積は約28ヘクタールに達する。そして遺丘の高さは14m近くあった。それゆえに、ここでの発掘調査は、イラク隊をはじめ、オーストリア隊やイタリア・ドイツ共同調査隊、日本隊などの各調査隊によって行われた。イラク隊の調査は主に遺丘の北部頂上区域と北西部区域で、オーストリア隊の調査は遺丘の南西部に広がる裾野の端で、そしてイタリア・ドイツ共同調査隊の調査は遺丘の最北部斜面上で行われた。日本隊は、遺丘の東部斜面上の最上部から裾にかけて3ヶ所の発掘区域(A区、B区、C区)を設け、それぞれの区域に複数のトレンチを入れて調査を行った。これら各国隊の調査によって、ハッスーナ期からイスラム時代に至る断続的な居住層や文化層が確認され、採集された土器片の情報とあわせて、この遺跡の歴史的変遷や遺丘の成り立ちを推定する上で有益な情報が収集されるに至った。
この場所での最初の居住はハッスーナ期に始まり、ハラフ期とウバイド期に部分的な居住が行われた後、前4千年紀に至り、所謂ガウラ期にも居住があったことがわかっている。この場所で本格的に広範囲に居住が行われたのは前3千年紀のニネヴェ5期に至ってからで、居住は前3千年紀の後半の時期まで断続的に続き、この前3千年紀を通じて遺丘の基本的な形状が形成されたことが判明、そして前2千年紀前半から中頃にかけて、幾層かに重なる住居址の堆積によって遺丘自体の高さが3~4m上昇、次いで中期アッシリア時代の居住址の堆積がさらに遺丘の高さを上昇させたことも明らかとなっている。そして、新アッシリア時代のある時期に至って、遺丘上での居住が再開され、ヘレニズム時代、ササン朝ペルシャ時代、そしてイスラム時代と断続的に続いた居住が遺丘の高さをさらに5m近く上昇させたことも判明している。この場所における最後の居住として記録できるのは、発掘調査当時にまだ住まわれていた、ヤズィーディの人々の、日干しレンガづくりの建物群である。遺丘の南部に広がっていたこの村の家屋群がもはや湖底であとかたもなく消え去っているであろうことは今、想像に難くない。
 テル・ジガーンC区出土ハブール土器
テル・ジガーンC区出土ハブール土器日本隊が調査した遺丘東部斜面上のA区では、ハッスーナ期の層があり、アラビア語でタウフと呼ばれる練り土の壁が発見された。日干しレンガが使われた、ニネヴェ5期から前2千年紀中頃までの居住層の堆積も確認され、なかでも目を引くのは壕の存在で、前3千年紀後半に年代付けられる膨大な土器の破片が壕のなかに捨てられ、スロープ状に堆積していた。一方、ティグリス河の支流によって形成された崖の縁にあるB区の発掘で確認されたものは、ニネヴェ5期の日干しレンガの建物址を上方から切り込み破壊するかたちで造営された、前3千年紀後半や前2千年紀中頃の、あるいはイスラム時代の、幾つかの墓や土器窯などであった。斜面上に5つの方形トレンチを設け発掘されたC区では、日干しレンガが使われたニネヴェ5期の居住層と、前3千年紀後半の文化層の存在が認められ、そして、石積みの基礎の上に日干しレンガを積んで構築された建物址を包含しハブール土器やヌジ土器を出土する前2千年紀の前半から中頃にかけての複数の居住層や、中期アッシリア時代の居住層などが連続層位として確認されている。C区の、遺丘斜面の中腹と裾の間に設けられたトレンチでは、7.5mの深さまで掘り進んだ段階で、遺物を含まない自然面、つまりいわゆる地山に到達している。
C区の調査終了後、遺跡にあった日干しレンガづくりの調査隊宿舎に発掘した遺物や調査隊の物資、機材などを保管して我々日本隊は一時帰国したが、その間にすでに貯まり始めていたダム湖の水位が急激に上昇して水が宿舎を襲い、建物を洗い流してしまった。幸いと、遺物や機材や多少の物資は泥まみれになって残ったが、機材のほとんどはもはや使用にたえ得るものではなかった。こうして、日本隊はさらに上流の遺跡の調査へと赴いた。
テル・ジガーン遺跡、主要参考文献
井博幸他「テル・ジガーン第一次発掘調査報告」『ラーフィダーン』第5-6巻(1984-85)、他『ラーフィダーン』第13巻(1992)に掲載。