


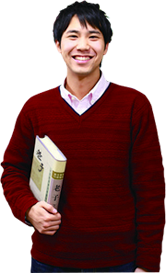

【世田谷キャンパス】
〒154-8515 東京都世田谷区世田谷4-28-1
電話:03-5481-311103-5481-3111 <交通アクセス>
【町田キャンパス】
〒195-8550 東京都町田市広袴1-1-1
電話:042-735-3111042-735-3111 <交通アクセス|バスダイヤ>
【多摩キャンパス】
〒206-8515 東京都多摩市永山7-3-1
電話:042-339-7200042-339-7200 <交通アクセス|バスダイヤ>

Copyright © Kokushikan University, All Rights Reserved.




