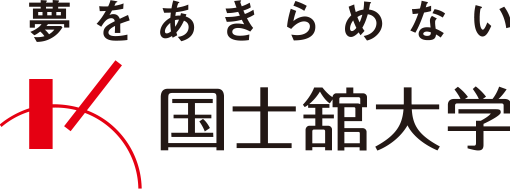編集部:国士舘大学の法学部法律学科では、どのようなことを学ぶのでしょうか?
国士舘大学の法学部には、現行法の解釈に比重を置き、伝統的な法学教育を行う「法律学科」と、企業法務、国際ビジネス法務、知的財産などを柱として、ビジネスに関わる法を実践的に学ぶ「現代ビジネス法学科」の2つの学科があります。私は主に法律学科で教えています。
「法律学科」では、憲法、民法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、商法のいわゆる六法を中心に、その法律の主旨や解釈など、基本的な部分をしっかり学んでいきます。ただ、私たちが目指すのは、法律の専門家になるための学びだけではありません。法律の学びを通して、基礎的な知識と思考力を身に付け、社会で役立つ有用な人間を幅広く育成したいと思っています。将来の進路としては、警察官、消防官、自衛官、市役所などの公務員を志望する人が多く、また、民間の企業に就職する人も少なくありません。
編集部:いろいろある法律の中で、先生はどこを専門に研究なさっているのですか?
私は主に「犯罪者処遇法」という分野を専門に研究しています。といっても、そういう名の法律があるわけではありません。犯罪者の取り扱いに関する諸法律ということで、刑法、刑事訴訟法、刑事収容施設法、更生保護法などの他、心神喪失者等医療観察法や少年法など、幅広い分野の法律が関係してきます。
犯罪者処遇法の歴史からお話しましょう。もともと一定の行為を「犯罪」として、それを犯した者に支配者が刑罰を科す仕組みは世界中どこでも存在していましたが、とりわけ近世になり「法の支配」の原則が確立すると、一方で罪を犯した人の人権を保障しつつ応報としての刑罰を科していくことが求められるようになりました。こうした対応の下では、あまり「犯罪者の処遇」という発想は展開しませんでした。
ところが19世紀になって産業革命が起き、人口増加とともに都市が大きくなるにつれて、従来の応報的な刑罰や一般人への威嚇だけでは犯罪が減らず、むしろ常習犯や貧困を理由とする犯罪が増加していきます。そこで生まれてきたのが、「犯罪学」という分野です。人が罪を犯すにはそれなりの理由があるはずで、その原因を突き止めて取り除かなければ犯罪は防げないという考えです。この考えの下で、犯罪原因論の研究が盛んになったのです。そして、将来の再犯を防止するための犯罪者の改善・社会復帰のあり方が、刑事法の領域でも議論されるようになりました。ここに犯罪者の処遇についてを研究する「犯罪者処遇法」が登場してくるのです。
編集部:なるほど、重い刑罰を科すだけでは、次の犯罪は防げないという考えが出てきたのですね。
そうです。さらに20世紀半ばになると、「ラベリング理論」という新しい犯罪学の理論が出てきます。ある人が犯罪をすると、「犯罪者」というレッテルを公権力が貼ります。そのレッテルを貼ることで、人はかえって犯罪を繰り返すようになるというのです。つまり、「犯罪者」のレッテルを貼らないようにすることが、新たな犯罪の抑止につながるのだと。この考えに基づき「ダイバージョン(diversion)」という発想が生まれました。元になる動詞の「divert」は、英語で「逸らす」とか「転換する」という意味があり、司法システムの早い段階で罪を犯した者を解放し、場合によっては福祉などのシステムにつなぐことによって、再犯を防ごうという発想です。
警察、検察、裁判、矯正、更生保護といった要素から構成される日本の刑事司法システムも、基本的にこの2つの考え方、犯罪をした者に刑罰を科す「刑罰」システムと、なるべく刑罰を科さずに対応する「ダイバージョン」のシステムから成り立っています。
編集部:先生は犯罪者の処遇に関わる全般的なことを研究なさっているのですか?
私が研究しているのは、犯罪者処遇法の中でも、特に罪を犯した発達障害者に対する法的対応策の分野です。まず、断っておきたいのは、発達障害があるからといって犯罪を行いやすいわけではありません。ここは社会的な偏見につながる部分なので、決して誤解しないでください。
ただ、とりわけ自閉症などですが、先天的な脳機能の問題でコミュニケーションや社会性に障害があると、家庭での養育に困難が生じる、あるいは学校で先生や友達になじみにくいといった問題が出てくる場合があります。そうなると、家庭であれば虐待のリスクが高まり、学校ならいじめや不登校のリスクが高まります。これがエスカレートしていくと、社会から疎外されて居場所がなくなり、深夜徘徊などが始まって通常の社会システムから逸脱していき、二次障害として犯罪や非行に至る可能性が高まります。そして、発達障害のある人の場合は、犯罪や非行文化になじんでしまうと、なかなか社会に復帰するのが難しくなります。発達障害を緩和するための療育に加えて、犯罪や非行に対する矯正教育も必要になってくるからです。こうした人たちの社会復帰のための「居場所づくり」も含めた仕組みをどうやって作り上げていくのかが、今の私の研究テーマです。
編集部:大学の授業では、どのようなことを教えているのですか?
私が担当しているのは「犯罪者処遇法」の授業です。犯罪者の処遇は、警察の捜査や裁判の段階における「司法的処遇」と、刑務所や少年院などの矯正施設で行われる「施設内処遇」、社会の中で更生を目指していく「社会内処遇」の3つに大別されています。授業では、「犯罪者の処遇」とは何かという基本的な部分を理解した上で、それぞれの段階における処遇について詳しく見ていきます。
日本の刑事司法制度では、「刑罰」システムがある一方で、先に述べた「ダイバージョン」のシステムも各段階で用意されています。たとえば警察には「微罪処分」という制度があり、事件を捜査しても一定の軽微なものについては、検察に送らずに事件を終わらせることができます。
また、検察に送られる事件のうち約6割は起訴猶予になり、残る事件については裁判まで行って有罪になっても、多くは罰金刑です。また、懲役刑も約6割は執行猶予が付きます。現在、毎年100万件ほどの罪を犯した人の事件が検察に送られていますが、その中で実際に刑務所に入るのはわずか2万人弱です。その他の事件の多くには「ダイバージョン」のシステムが機能して、実刑には至りません。そのような処理をしても犯罪から生じた社会的葛藤は解決でき、加害者の更生にも役立つだろうという配慮からです。
編集部:罪を犯したからといって、すぐに刑罰にはならないわけですね。
はい、「一罰百戒」ではないというところが、日本の刑事司法システムの特徴です。たとえば、おにぎり一個を盗むと、刑法上は235条の窃盗罪に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになっています。でも実際には、必ずしもそうした刑罰が科されるとは限りません。いま言ったように多くは警察で微罪処分で処理されて、それ以上は罪に問われないからです。何度も繰り返せば別ですが、一度や二度では刑務所に行くには至りません。もちろん彼らは犯罪をしたという点では応報的な制裁を受けるべき立場にも置かれており、刑罰という形でその責任を取らせる仕組みは存在しているわけですが、他方でそうした「犯罪者」のレッテル貼りを回避するとともに犯罪者の更生を促すシステムも日本の刑事司法にはあるのです。
刑事司法のシステムを考えるとき、犯罪者に罰を与える「応報刑論」と、改善して社会に戻す「改善刑論」と、2つの考え方があって、どちらを採用するかで世界中で議論が起きました。日本でも論争はありましたが、簡単にいうと「どっち付かず」という形をこの国は取っています。一応「応報刑論」に軍配は上がっていますが、その中でも可能な限り「ダイバージョン」のシステムを働かせるとともに、刑務所や保護観察においても社会復帰のための処遇をなすべきという考えに立脚しています。つまり犯罪者に対する「罰すべし」という要請と、「改善させるべし」という要請の双方が、絶妙なバランスを保つ形でこの国の刑事司法システムは成立しているのです。ある意味、この双方は矛盾しているのですが、矛盾を抱えたままシステムが存在しているということをきちんと見ることが、犯罪者処遇法では大切だと思っています。
編集部:その「矛盾」の部分について、もう少し詳しく説明していただけますか?
罪を犯した人間を罰する考えの基にあるのは、あなたのやったことは許されない、けしからんだろうという「善一悪」の評価基準です。ところが、犯罪学の分野は、医学、教育学、社会学、心理学などの学問をベースとしており、そうした知見を基にして、この人が犯罪をやったのは「素質や環境」などに要因があるというのです。もし、犯罪をやった要因が「素質や環境」にあることが証明されれば、それは経験科学的な論証なので、評価基準は「善一悪」ではなく「正一誤」になります。そして、「善一悪」の基準と「正一誤」の基準は必ずしも相容れるものではありません。あるものが正しいからと言って、それが善いとは限らない。逆に、あるものが間違っているからといって、必ずしも悪いとは限らない。人間の世界には、どちらか一方の価値基準では割り切れないことがあります。学問としての犯罪者処遇法はあくまでも人間を扱うので、その評価には「善一悪」と「正一誤」の矛盾が併存しうるのです。刑事司法システムにあるこの矛盾を無理に解消しようとするのではなく、矛盾を内包したまま理解することが大切なのだと、この分野を研究して私は思い至るようになりました。
編集部:学生たちは、ゼミではどのようなことを学ぶのでしょうか?
1年次にはノートやレポートの書き方など大学での学習法の基礎を学び、2年次になってからのゼミで少しずつ専門の分野に入っていきます。ちなみにゼミ以外には憲法、民法、刑法が1年生の必修科目となっていて、それぞれの基礎を学びます。国士舘大学の法学部では段階を踏んで徐々に知識を得ながら理解を深めていきますので、最初は特に法律の知識がなくても心配する必要はありません。
3年次には、主に「犯罪者処遇法」の基本である刑罰とダイバージョンの仕組み、そして、司法的処遇、施設内処遇、社会内処遇の内容について学んでいきます。たとえば、社会復帰のために望ましい受刑者の処遇はどうあるべきか、といったことを自由に考えて、発表してもらいます。それに対して総評やディスカッションを行い、話し合いながら理解を深めていきます。アイデアソンといって、自由にアイデアを出し合ってまとめるようなこともやります。そして、3年次の後半には、卒業論文につながるようなテーマで研究を始めて、4年次の初めには自分の研究テーマを決め、卒論にとりかかってもらいます。
編集部:こういった座学の他に、施設の見学などにも行かれるのですか?
そうですね。犯罪者の処遇は生身の人間を扱うものなので、私としては刑事司法の現場を見ることを大切にしています。たとえば、2年次のゼミでは少年法も扱いますが、ここでは実際に起きたある事件をテーマに取り上げます。だいぶ前になりますが、ある少年が河川敷で非行少年のグルーブに殺害されるという事件が起きました。それを少年法の学修に関連づけ、事件を未然に防げなかったのかをゼミのみんなで考察していきます。警察、児童相談所、学校、それぞれがどのように動けば犯罪が防げたのか、被害者を救えたのか。非行などに対応する様々な仕組みを学びながら考えていきます。
そうすると浮かび上がってくるのが、多機関連携の重要性です。警察、児童相談所、学校が連携すれば、もしかすると事件を防げたかもしれない。で、実際にこういう話をすると、「現場を見てみたい」という学生が出てきます。それで2019年の夏は3年生のゼミ合宿で、北九州市に行きました。北九州市では多機関連携の取り組みが進んでいて、同じフロアに児童相談所と教育委員会の出先機関、警察の少年サポートセンターが入っています。そこを見学して、学生には担当者から現場の生きた話を実際に聞いてもらいます。
また、これは法学部全体の行事ですが、1年生のときに「刑事司法機関見学バスツアー」というものを行っています。年に2回あって、2019年は神奈川県と埼玉県に行きました。現地では、地方検察庁と地方裁判所、県警本部や警察署などを見て回ります。裁判所で刑事裁判の仕組みや裁判員制度の話を聞いたり、検察庁で現役の検察官の話を聞いたり、県警では警察官の採用試験の話なども聞くことができました。実際に聞くと見るとでは大違いで、現場を見ると学生の目の色が変わりますね。北九州で刑務所を見学したある学生は、もとは警察官志望だったのですが、仕事に感銘を受け「自分は刑務官になりたい」と言ってきました。
編集部:今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの授業がオンラインになりました。 先生はどのような形で授業を行いましたか?
今年の学生たちは、本当に大変だったと思います。その中でも、通常の授業と変わりなく受けてもらえるように、私なりに最大限の工夫はしました。講義に関してはパワーポイントの資料を作り、そこに動画と音声を乗せたものを国士舘大学の「manaba」というサイトにアップして、視聴してもらいました。ゼミの授業はZoomというビデオ会議システムを使って行い、ブレークアウトセッションを使って学生同士でディスカッションもしてもらいました。最近は少しずつ対面の授業も始まっていますが、全員マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保って感染対策を施しながら授業を行っています。
編集部:先生はどのようなきっかけで、法律の道に進むようになったのですか?
実は、高校生のときは法学部に行く気はまったくなく、文学部に行くつもりだったんですね。SF小説の作家になりたかったもので。しかし、親から就職がいいから法学部に行けといわれて、とりあえず法学部に入学しました。自分でいうのも何ですが、あまり褒められた動機ではありませんね。
大学に通い始めてもどの法律を学んでいいかよく分からなくて、迷っていました。そんな中で「犯罪者処遇法」というものがあることを知り、なんだろうと興味を持ち、ゼミを選択したわけです。もともと小説を書きたかったので、人間に興味があったんでしょう。どんな人が犯罪者や受刑者になるのだろうって、そういう関心からこの道に入っていきました。
ただ、なんでも中途半端は嫌いなので、やるからには徹底的に学びたいと思い、必死で勉強しました。そのおかげで大学院はトップの成績で合格し、奨学金もいただくことができました。
編集部:最後になりますが、大学の学びを通して、どのような人材を育てたいとお考えですか?
いまはネット社会になって、いろんな情報が飛び交っているので、まずは正しい情報を取捨選択できるリテラシーを身に付けてほしいと思っています。情報を鵜呑みにするのではなく、その背後にあるものを見極める目と、的確な分析力を持ってほしいですね。それがいちばん学生に求めることでしょうか。
それから警察官を目指すということであれば、倫理観はもちろんですが、その倫理観を支えるための「物事を多面的に把握する姿勢」も大事だと思っています。先ほども述べましたが、犯罪者処遇の世界は「善一悪」と「正一誤」の評価基準が矛盾したまま存在しています。その中で大切なのは、一方からではなく、他方からも物事を捉えて、多面的に見ていくことだと私は思います。犯罪は加害者だけの問題ではなく、被害者もいて、それを受け取る社会の問題でもあり、そこから生じた社会的葛藤の解決が求められるからです。一方向だけから物事を見ていては、なかなか解決しません。特に刑事司法の道に進む学生には、ぜひとも「物事を多面的に見る」ことを心がけてほしいと思います。
あとは泥臭くてもいいので、くじけずに頑張って生きていく人になってほしいです。独りよがりの人間にならずに、人のために尽くせる人として、社会で活躍してほしいと願っています。
宍倉 悠太(SHISHIKURA Yuta)准教授プロフィール
●修士(法学)/早稲田大学 大学院法学研究科 公法学刑事政策専修 博士後期課程 単位取得満期退学
●専門/犯罪者処遇法、少年法