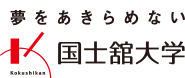編集部: 国士舘大学の21世紀アジア学部で、学生はどのようなことを学ぶのですか?
「21世紀アジア学部」は、アジアおよび世界で活躍できる人材を育てることを目的として2002年に開設されました。「アジアが熱い」という潮流の中で生まれた学部ですが、僕個人としては、対象はアジアに限らず世界に広がっていると思っていて、グローバルスタディーズの中におけるアジア地域研究として捉えています。
日本人にはどちらかというと単一民族意識が強い傾向が見受けられるのでどうしても内向きになりがちで、学生が世界に目を向ける場合でも、いきなり西洋というのはハードルが高いと思います。でも、アジアであれば身近な存在として感じられるし、わりと気軽にエキゾチックな体験ができる。そういう意味で、アジアは“リミナル”な場所じゃないかなと僕は思っています。リミナルというのは、馴染みのない世界と馴染み深い自分たちの生活世界の中間にある場所で、象徴人類学的ないし民俗学的な言い方をすれば、妖怪とか妖精の類いが出てくるファンタジーに比類した世界です。日本と西洋の間にある“リミナル”な空間であるアジアに、テーマパークに行くようなノリで旅に出て、その中で学術的なツールとしての調査技法や研究のコツを身に付けながら自己探究を行う。それが次のステップとしての国際人の育成につながっていくと思っています。
21世紀アジア学部では、どの学生も一度は在学中に海外へ出ることになっています。卒業生に聞くと、それがいい経験になったと言います。別に長期の留学ではなく、短期の語学研修でもいいんです。とにかく中国や韓国、インドネシアなど、目標設定をして行ってみる。すると現地に友達ができて、思いがけず自分の世界が広がった、みたいなことを体験するわけです。それだけでも人生の財産になりますね。身近に行ける場所になり得るし、さまざまな文化社会的ないし歴史的な価値観がせめぎあい、混沌としているアジアのダイナミックなカオスに触れることで、グローバルな視野が開けてくるのです。

編集部: 先生はこの学部で、どのような授業を担当されているのですか?
学部では地域研究の諸科目を受け持っています。「アジアの文化」とか「異文化理解」とか「日本のポップカルチャー」とかですね。ただ、いきなり小難しい講義をしても、学生はなかなか興味を示しません。政治や経済の話をしても、自分とは遠い場所にあると感じてしまってピンと来ないのでしょう。ですから、僕は授業でも、ポップな話(例えばJPOPやKPOPの事情など)から入っていくようにしています。例えば日本や韓国のタレントの話なら、みんな知っていますから。どうやってアイドルを売り出すのか、プロダクションはどのようにして売上を上げていくのか、そういう話になると学生の目が光ります。そこを入口にして学びに入っていくと、ものすごく分かりやすくなります。
異文化理解のクラスで話をするときも、「侘び寂びの世界は千利休が中国の茶道を和式に再製して……」みたいな話をしても、学生は興味を持ちません。でも、知っているK-POPグループの名前を出して、彼らが日本にやってきて、日本語を勉強して、韓国と同時デビューを果たして、みたいな話をすると、日本と韓国の関係性とか文化が流入してくる過程をよく捉えることができる。そこから話を広げて、儒教が日本に入ってきた頃の大和朝廷はどうだったとか、遣唐使を派遣した頃の日本人がいかにして大陸文化を吸収したかという話、あるいは先の茶道の侘化・寂化の話につなげていきます。ポップカルチャーを入口に、身近な事例を使いながら、文化の構成のされ方、変遷のメカニズム、伝搬のプロセスなどの学びに入っていき、文化人類学の研究のコアな部分へと学生たちを導いていきます。

編集部: 授業にOBやOGを招くこともあるそうですね。
これにはどのような目的があるのですか?
はい、先日も学部第一期生のOGを授業に呼んで、話してもらいました。彼女はワーキングホリディの制度を利用してオーストラリアに行きました。そこでしっかり留学アドバイザーの資格を取りました。で、帰国後どうするのかと思ったら、今度は青年海外協力隊でスリランカに行きます。すごい行動力ですよね。それが終わったら日本に戻ってきて、いまは別の大学で海外支援のことを専門に学んでいます。
開発教育のボランティアにも携わっていた彼女は、子どもの教育支援をやろうと思い立ってスリランカに渡ったわけですが、その支援の内容や、海外支援の精神性のすばらしさなどを教えてもらいました。また、彼女はスリランカのシンハラ語ができるようになったのですが、いかに短期間で語学を修得するかという、青年海外協力隊の語学の学び方などについても話してくれて、すごくためになりました。
実体験から出た話なので、学生の心に響きますね。僕なんかの講義よりも、よっぽど学生諸君の心に刺さるはずです。「一度うちに来て、授業で話してくれ」とずっとオファーしていたのですが、今回ようやく願いがかないました。

編集部: 生田にある岡本太郎美術館にも学生を連れて行かれたそうですね。
これは21世紀アジア学部の特色である「アウト・オブ・キャンパス」の一環として行っているもので、僕の授業を履修して下さっている学生に声をかけて、有志のメンバーで行きました。日本の代表的な芸術家である岡本太郎が、どんな思いで創作活動をしていたのか、その文化創作の現場に触れ、アートの力を実感し、そのエネルギーを吸収してもらうのが目的です。
だから、ただ見学するだけではありません。事前に岡本太郎のことを調べて、現地に行って、彼がどんな思いで創作していたのかを肌で感じ、その後に事前学習したときとどんな変化が自分の中に生まれたかを探究してもらいます。作品が誕生する現場を見て、何かを感じてほしいという思いで、年に2回ほど行っている授業です。岡本太郎美術館の他にも、同じ地元町田市の自由民権資料館や、都内なら江戸東京博物館や、ポップカルチャーの街である秋葉原や渋谷や、庶民感に溢れる大阪の新世界、あるいは沖縄はコザの街ぐゎ~へ出かけることもあります。教室だけで学びを完結せずに、キャンパスを飛び出して学生に刺激を与えたい、そんな思いで続けています。

編集部: ゼミの学びには、どんな特長があるのでしょうか?
実は僕自身、昨年度は1年間ブラジルに学びに行っていたので、2019年度は専門ゼミを持っていませんでした。でも、今年の4月(2020年度)から新たに3年生のゼミを受け持つことになっています。すでに募集が終わったところですが、なかなか面白そうな学生が集まってきてくれています。例年僕が担当する専門ゼミでは『地域研究』をメインテーマに思考力や創作力を高めながら、メンバー各位に独創性溢れるマイ探究プロジェクトを構想・企画してもらいます。そしてそれができたら、現地調査をしにマイフィールドに遊学してデータを収集し、得られた成果を民族誌形式(ethnographic)にまとめてもらいます。自分にしかできない、自分だからこそできる、大学レヴェルの研究調査を達成し、何らかの形で地域社会に貢献し得る人材へと自身を楽しく育成するよう、動いてもらいます!
21世紀アジア学部には、他大学にはないユニークな特色があります。それは卒業の手段として、「卒業論文」以外に、「活動報告」や「創作」が選べるということです。必ずしも論文にこだわる必要はありません。たとえば、陶芸家のところに修行に行って匠の世界を体験し、陶芸の作品を作って提出するというやり方もあります。作品と、なぜその作品を作ったのか、文化価値はどこにあるのかなどを4000字以内の報告書にまとめれば、それが卒論扱いになります。同様に、自分が行ってきた活動を報告書にまとめて卒業報告書にすることもできます。アジアの文化を理解したうえで、「卒論」「活動報告」「作品」の3つの形を用意してあるのはすごいことだと思います。世界中を探しても、このように卒業の形が選べるという大学は、なかなか見当たらないでしょう。そういう意味では、自分の創作能力や自由な発想を思いっきり発揮できる学部です。何か面白いことをやってやれ、みたいな人には向いている学部だといえますね。

編集部: 先生ご自身は海外の大学を卒業されていますね。
どんなことを学びに行かれたのですか?
僕はワシントン州立大学に入って、はじめは政治学を学んでいました。でも、途中で人類学が面白くなってきて、そちらの方に転向しました。というのも、人類学の先生方がイキイキしていて、学びを楽しんでいるように見えたからです。たとえば、恩師が最初に連れていってくれたフィールドワークの場所は、なんと監獄でした。それも服役期間が一ライフタイム以上といったすごい人たちが入っているところ。そこで学生たちに囚人へのインタビューをさせるんです。
先生は楽しそうにシャワー室を見せてくれたり、囚人たちがどうやって外の世界と連絡を取り合うか、そのからくりを教えてくれたりするんですが、僕たちはもう恐くて、テンションが高かったのを覚えています。昔ながらの映画に出てくるみたいな鉄格子のはまった監獄で、囚人の喚き声も聞こえてくるわけです。そんな中で僕たちは囚人へのインタビューを試みました。自分の太腿ほどもある腕を持つゴツいインフォーマントに、おそるおそる聴き取りをするんですが、でも、外見からは想像もつかないくらい自分が対話したその人は、見かけはとても穏やかで、とても大罪を犯したなどとは思えませんでした。自分の囚人に対する印象もガラッと変わりましたね。先生の狙いは、「罪人=悪人」という固定観念から僕らを解放することにありました。確かに罪は犯したけれど、その背景には罪を犯さざるをえない社会的な状況がある。親がアル中だったり、DVを受けていたりと、そういう環境があることを教えてくれたのです。そうした発見を現場でイキイキと体験できたわけです。とにかく魂にビンビン響いてくる感動的な授業でした。「ああ、僕も将来こんな先生になりたい」って、心の底から思いました。

編集部: そこから人類学の学びを深めていかれたのですね。
はい、その後は長年憧れていたアメリカの先住民族の文化にも接したいと思い、アリゾナ大学の大学院に進学しました。修士課程を取ったのですが、幸運なことにホピ族のメンバーだった恩師にもついて学ぶことができました。まさに、自分が尊敬していたフランスの大御所文化人類学者のクロード・レヴィー=ストロース先生が『野生の思考』で著した先住民たちの感覚、感性に触れることができました。
アメリカは、グランドキャニオンの向こうに広大な砂漠が広がっていて、その砂漠の中に「メサ」という台地があり、その上にプエブロ系と呼ばれるネイティブが住んでいたりします。彼らは千年以上も前から台地に城のような集落を築き、昔ながらの暮らしを続けています。日本の神道と同じようなアニミズム信仰を持ち、「カッチーナ」という八百万の神を信じています。ネイティブの恩師にはそういうところに連れて行っていただき、学ばせていただきました。
編集部: その後にカナダの大学に移られますね。そこでは何を研究なさったのですか?
博士課程は、ヴァンクーヴァーにあるブリティッシュコロンビア大学に進みました。それまで先住民の研究をしていたのですが、ここらで自分が生まれた日本の文化についても考えてみたいと思ったのです。その大学で教鞭をとっていた先生が、日本のポップカルチャー研究の第一人者で、日本のデパートを研究されていました。ミリー・クレイトンというその教授に師事して、ポップカルチャーの中のアイドルの研究をやろうと思い立ったんです。
アイドルという存在には、ある意味ホピ族の神々や日本の八百万の神に通じるような神秘性があります。アイドル産業は、まさに若手タレントたちによって放出されるミスティックなキャラクターやクオリティーを売りにするもので、普通の男の子や女の子を崇拝(フェチ)の対象になる存在へと仕立てていきます。それまでの先住民研究を含めて、僕の中でいろんなものが「アイドラトリー(偶像崇拝)」という題目を中心につながりはじめました。それで世界初の文化人類学的な視点に立ったアイドル研究に取り組みました。なぜみんなアイドルを崇拝するのかということを、人類学的なアプローチで分析し、研究してみたのです。

編集部: 昨年1年間、ブラジルに行かれていたようですが、
ここではどのような研究をなさったのですか?
ブラジルには、本学の特別研究派遣の制度を使って行きました。沖縄とブラジルにおける新たな民族アイデンティティの形成について比較研究することが目的でした。
というのも、ここ10年ほど、僕は沖縄の新しい民族意識の形成について研究していました。沖縄では普天間基地の辺野古への移転問題以降、「自分たちは先住民である」という新たな民族意識も、若手を多く含む一部の「県民」の間に生まれつつあります。琉球人としてのプライドやアイデンティティを取り戻そうという動きですね。
一方、ブラジルのアマゾンの先住民にも同じようなことが起きていて、若い世代を中心に失われつつあるアイデンティティをグローカルな自己表現を通して再生していこうとする動きがあります。今どきのファッションに身を包んだ若い子が、伝統的な羽根の耳飾りやビーズのミサンガを付け、ハイブリッドな自己演出を繰り広げているのです。本人たちに聞いてみると、必ずしも意識的とはいえないまでも、そういうアイテムで民族的な誇りを表現しているのだそうです。こういう沖縄とブラジルの先住民系の「ネオエスニック」な動向を比較研究するためにブラジルに行ってきました。
ただ、僕には一つだけこだわりがあって、日本の研究者がやってきて一方的に先住民を被験者のように扱うような研究はしたくないんです。それで現地にいるネイティブの先住民の研究者と手を組めなければ、この研究は止めようと思っていました。色々と働きかけた結果、幸運にも4名の協力者を派遣先のブラジリア大学で募ることができて、共同研究という体裁で民族誌のフィールドワークを実施することができました。
編集部: オックスフォード大学に招かれて講演に行かれたそうですね。
ブラジルでの研究成果を発表されたのですか?
はい、そうです。僕の知人がこの研究が示唆する『文化と民族的アイデンティフィケーション』関連の問題を見て、「これは面白い、ぜひうちの研究所でも発表してほしい」と言ってきたので、参加させていただきました。今はこの研究をまとめて、学術論文にしているところです。
僕にはリタイヤするまでにやりたいことがあります。それは、国士舘大学のこのキャンパスにブラジルの先住民の研究者と琉球の研究者をお招きし、シンポジウムを開くことです。そして、この研究を次世代にどう託していけばいいかを議論したい。もし可能であれば、これから本学に入ってくる若い人たちと一緒に、未来の学術的探究や社会活動の基盤を作れたらいいなと思っています。そんな思惑を胸に、インテレクチュアルなネットワークを広げる意味でも、こうした会合には呼ばれれば積極的に応じることにしています。

編集部: 最後におうかがいします。文化人類学の学びを通して、
どのような人材を育成されたいとお考えですか?
まず、大学には自由な時間があります。その時間を活用して、学生たちには「真剣に遊んでほしい」と思っています。今の、特に日本の若者たちは果たして「真剣な遊び」=「文化の創作に繋がるようなまともな学び遊び」をしているか、甚だ疑問に思います。制度的な抑圧や情報洪水の渦中に置かれ、「遊び心」を忘れてしまっているように見受けられ、国(民国としての)の将来や子々孫々のライフワールドの予期的な有様について憂えてもいます。『ホモルーデンス』という書を著したヨハン・ホイジンガは「人間は本来遊ぶ動物であり、遊びは文化を創りだす原動力になり得る!」と言っています。もちろん基礎的な知識や研究手法を修めることは大切ですが、それを身に付けたうえで「遊学」というスタンスを通して今の自分という殻を飛び出して冒険し、世界とよく対話しながら、楽しく人文を育む自身と全力で向き合ってほしいと思います。子ども心に帰って、好奇心の赴くままに、自由であること=即ち自身の選択と行動に悔いなく生きる(活きる)ことを楽しんでいただきたいのです。
学生たちにはそうやって様々なことを経験しながら「魂の入った人間」として成長してほしいと願っています。何事をするにしても魂を打ち込んでやってほしい。これは国士舘の建学の精神、あるいはそのもととなった吉田松陰の「至誠」というコンセプトにも通じる考えだと思います。自分の真心に忠実になって、誠を尽くして生きる。遊びたいなら遊んでもいいけれど、全力を尽くして真剣に遊び、やがては創作能力を以て世界に貢献し得る人材へと自己開拓を図るということがこの上なく大切だし、今だからこそそんな資質が国際的にも求められているのだと実感しています!
僕のところで学んだ学生は、さまざまな進路に進みます。観光会社に就職する者もあれば地方公務員になる者あり、また海外に飛び出して教育や地域開発に携わる先輩もおられます。他方、アニメーターやテレビのAD、声優やファッションモデルになる先輩もおられます。「自分はサーフィンしかできない」と言っていた一期生の某先輩は、サーファーになりながら護岸に取り組むNGOを立ちあげ、頑張っています。何を仕事にするにしても、とにかくよく思考を凝らし、全力で打ち込みながら、たった一度の人生を精一杯紡ぎ、命を育んでほしい。そして、家庭を持ったら、自分の子どもたちにも命の輝きを伝えられる親になってほしいと思います。
生きていることの手触りが希薄になってきた今だからこそ、時代に逆行して、根本的な命につながるところを大切にしてほしい。何事にも魂を入れて、生きること、そして創る喜びを全力で楽しめる人間になってもらえれば、それ以上何も言うことはありません。

青柳 寛(AOYAGI Hiroshi)教授プロフィール
●博士(人類学)/ブリティッシュ・コロンビア大学 人類学および社会学 博士課程修了
●専門/文化人類学