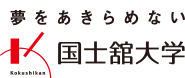編集部: 国士舘大学の政経学部で、学生たちはどんなことを学ぶのですか?
国士舘大学の政経学部が目指すのは、政治、経済の専門的な知識を活用する力を身に付け、多様化する現代社会の中で中心的な役割を担う人材を育成することです。そのために基礎学力としての知識や理解力、社会や国家、国際社会のあるべき姿や課題を論理的に考え、判断する力を身に付けなければなりません。また、自分の考えを他者に分かりやすく説明できる表現力や、協働する姿勢も必要になります。これらの目的を達成するために、一人ひとりに目が行き届くきめの細かい指導を行っています。本学部には「政治行政学科」と「経済学科」の2学科があります。幅広い分野での知識教養を身に付けるため、両学科のハードルを低くし、双方の科目を履修できるようになっています。

編集部: 先生は、主にどのような授業をご担当されているのですか?
私が受け持っているのは、2年生の基礎ゼミと、3年生の専門ゼミで、来年度は4年生のゼミと卒論指導も受け持つ予定です。2年生の基礎ゼミでは、まず日本や世界の経済の動きを幅広く見渡し、専門的な学びの下地を作ります。最新の経済ニュースのチェック、グループワーク、討論、プレゼンなどをとおしてアクティブラーニング的な授業を行っています。一方的に教えてもなかなか知識は身に付きません。受け身でない自主的な取組みをとおして初めて身に付くものだと思います。ただし、スポーツと同じで学問研究にもルールがあります。データや文献の探し方、扱い方、他の人の発見や意見の取り入れ方など、守るべきアカデミック・ルールは繰り返し伝えて自覚を促しています。
ゼミの他には、フランス語の初歩から中級までを受け持っていて、少人数クラスでコミュニケーションを中心に双方向の楽しい授業になるよう工夫しています。4技能の向上や異文化理解はもちろんですが、私が特にこだわっているのは、外国語に直訳・逐語訳したときまるきり通じなくなったり別の意味になったりするのはどうしてか、ということに気づいてもらうことです。言語が違えば発想が違い、世界を見る目が違ってくるということを実感してほしいと思っています。
外国語学習とは、住み慣れすっかりなじんでいる言葉の家から外に出て、不可思議な空間で右往左往することです。しかし、そうやって私たちは自分の世界を広げられるのです。

編集部: 3年生の専門ゼミでは、どのような学びを行っているのでしょうか?
専門ゼミでは、EU経済を扱っています。テーマの大枠はこちらから提示しますが、そこから細かい問題を切り出すのは学生自身です。EUの成立過程や制度的仕組み、市場統合やユーロの導入過程、共通農業政策、エネルギー・環境政策、英の離脱問題、日本との経済連携協定など多岐にわたるテーマから各人がリサーチクエスチョンを探し、それについて自分でデータを探し、文献を読み、考察を加え、発表します。そこに私や他の学生が質問を投げかけます。それに対して学生は一歩進んだリサーチをし、次の発表に備えます。学生にとって決して楽ではなく、しばしば苦渋の表情も見られますが(笑)、こうやって繰りかえしていくと、どんどん学びが深まり、彼らの頭がイキイキと回転してくるのが分かります。このプロセスを何よりも私は重視しています。

編集部: 先生がEUに関心を持ち、研究するようになったのはなぜですか?
私は日本の大学で修士課程を修了した後に、3年間の予定でフランスに留学しました。パリ大学の博士課程で専門の哲学の勉強をしていたのですが、それ以外にヨーロッパの文化社会や政治経済があまりにも面白くなってしまい、日本に帰れなくなってしまいました。結局1984年から96年までの12年間、博士論文を先延ばししながら(笑)、留学生用の労働許可を取得して、日本のマスコミの取材の下準備や通訳をしたり、日本の雑誌向けに時事問題を扱った記事を書いたりしていました。なぜそれほど面白かったかというと、すぐ目の前で歴史が作られていたからです。当時のヨーロッパは市場統合と通貨統合に向かっていくさなかでした。ベルリンの壁が崩壊し、東欧で革命が起き、冷戦が終結し、東西ドイツが統一され、ECがより大きなEUとなり、新しいヨーロッパへの希望と不安が錯綜していました。
私が住んでいた学生寮には、ヨーロッパの各地から学生が集まっていました。彼らは、最初はヨーロッパの統合に対して半信半疑でした。ところが、実際に統合が進むに連れ、自分たちの将来をヨーロッパ規模で考えるようになってきたのです。ヨーロッパ人としての意識の芽生えを、私は彼らから感じ取ることができたのです。
編集部: ご自身の留学体験から、EUへの関心が生まれたわけですね。
そうなんです。フランスとドイツは隣国同士でありながら、幾度となく戦争を繰りかえしてきました。ところがその両国が、手を取り合って一つのヨーロッパを作ろうとした。欧州のあちこちには紛争もあり、独裁政権もありましたが、「共同体への加盟」という未来に向かって歩む中で、民主制へと移行し、紛争を解決してきたのです。その基盤となったのが、相互利益、共存共栄を実現する経済システムの構築でした。EUが身をもって示してくれたこと、それは平和・友好とは、経済というグラウンドが整備されてこそだということです。国家間、民族間に経済の壁というか溝がある状況で、精神的に平和や異文化理解や他者への寛容の精神を説いたところでうまくいかない。逆に、共通の経済的基盤を整えれば、それらは実現しやすくなる。もちろん、EUは今も格差や移民問題、ポピュリズムといった問題を抱えていますが、それを今後どう乗り越えるかも含めて、経済統合という「実験」は、私たちアジアの国々の未来を探るうえでも大きなヒントになると私は考えています。

編集部: 先生のご専門は哲学とうかがいました。
この分野ではどのようなことを研究されているのですか?
「哲学」と聞くと「何の役に立つの」と眉をひそめる人がいますが、実は普段身のまわりにある事柄について、少し深く考えてみることが哲学なのです。当たり前に思っていたことをちょっと疑ってみる。なぜだろうと考えてみる。そうすることで、今まで見えなかったことが見えてきます。
私が主に研究しているのは、20世紀フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルです。ただ、その思考を読み解くためには古代ギリシャまで遡らねばならず、特に不可欠なのは、17世紀フランスのデカルト、そして18世紀後半から20世紀前半にかけてのドイツ哲学です。デカルトは、すべてをいったん疑うことから出発して人間が身分や貧富の差にかかわらずなぜ根本的に平等なのかを合理的に説明した人。それを受け継ぐドイツ哲学のカント、ヘーゲル、フッサール、ハイデッガーらは世界と人間との関係について根本的な問いを立て、とことん突き詰めて考えました。
そして、私たち一人ひとりの経験は限られていても、それを越えて普遍的で本質的な知を見出すことは可能だと示してくれたのです。これは、人文社会科学の探求の基底をなすものです。ここ数年、彼らとサルトルとのつながりについて書き綴ってきましたが、 2020年の春には分厚い本となって刊行される予定です。
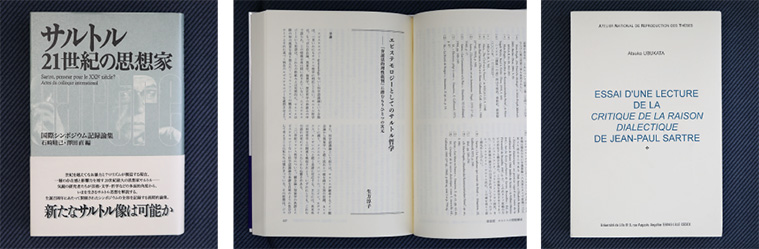
編集部: 2015年にパリで在外研究をされていますね。 ここでも哲学の研究をなさったのですか?
はい、2015年の9月から半年間、パリの国立近代草稿研究所で客員研究員として在外研究をさせていただきました。ここではサルトル関係の最新の資料をあたり、第一線の研究者や若い院生たちと情報を交換し議論を交わすことができました。あらためてじっくりとサルトルの本を読み直し新たな研究の構想を練る時間も持てました。また、留学時代の仲間との旧交を温める機会にもなり、たいへん有意義な時間を過ごさせていただきました。

編集部: ところで、哲学と経済学は、どこでつながっているのでしょう?
経済学や政治学といった社会科学は、人間の自己認識の学問です。古代ギリシャにおける学問の始まりは、自然への驚嘆と問いかけだったと言われます。どのような文明においても宇宙の成り立ちは神話によって語られてきましたが、タレスやデモクリトスといったイオニアの自然哲学者たちは、神話ではなく合理性によってそれを説明しようとしました。しかし、そのように問いを発し、合理的に思考しようとする精神というものを備えた人間とは何者なのか。こう問いを人間自身に向けたのがソクラテスです。こうして始まる人間の自己認識的な問いから、社会のさまざまな現象を解き明かす学問が分岐して生まれ、政治学、経済学、歴史学といった社会科学が生まれます。だから、すぐれた社会科学の研究は、根底に必ずや哲学があるのです。
そもそも、世界で初めて物品や金銭の交換・蓄積という現象を合理的に分析したのは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスです。彼は『政治学』という本の中で、当時誕生してまもない貨幣経済について、現代にも通じる鋭い考察を行っています。また、時代はちょっと下りますが、『国富論』を書いたアダム・スミスも、実は哲学の教授で、哲学書を書いています。 彼は18世紀フランスの啓蒙思想家と交流があり、大いにその影響を受けています。啓蒙思想の元となったのはデカルトですが、その流れを受けて18世紀の哲学者たちが発展普及させた“自由で平等”という人間観がなければ、こうした経済理論の発展もなかったことでしょう。
近代経済学の双璧をなすケインズとハイエクという二人の経済学者も、共に西洋哲学の伝統の上に立ちながら異なった目で人間活動を観察し、そこから対照的な人間観と対照的な経済理論を導き出しています。いわゆる「ケインズ革命」と「新自由主義」の違いは、根っこを見れば哲学上の違いです。哲学と経済学はその根底において、切っても切れない縁にあるのです。

編集部: 高校生の皆さんに向けて分かりやすい具体例を挙げてもらえますか?
たとえば、学校帰りにお腹がすいて、コンビニに寄ることがありますよね。そういうとき、皆さんは袋に入って中身の見えないおにぎりやお菓子を、何の疑いもなく平気で買っています。中に変なものが入っているとか、偽物じゃないかとか、疑いませんよね。なぜ疑わないのでしょうか。レジでお金を払うときも、考えてみれば、お金はただの金属の塊です。紙幣はただの紙切れ。スマホの電子マネーなんてもっと怪しい。でも、店の人は疑わずに受け取ります。なぜなんでしょう。当然のことのように思うかもしれませんが、そこには人類が何千年もかけて築き上げてきた“信用”によって支えられているシステムがあるのです。
ところで、その信用なるものは、どこに根拠があるのでしょう。今まで大丈夫だったから? 家族も友だちもみんな信用しているから? じゃ、そのみんなはなぜ信用するの? 他のみんなが信用しているから自分も信用するの? そこには「通念」というものが成り立っています。そう、信用は一種の社会通念なのですね。
編集部: なるほど。お金という経済を支えているのは、社会の信用なのですね。
そうなんです。ところで、反対に悪い評判が立つと逆のことが起こります。人々は自分でろくに確かめもせずに、悪い評判を信じて買わなくなります。これがいわゆる風評被害です。このような「自分で確かめずに信じている信念」のことを、哲学ではギリシャ語で「ドクサ」と呼びます。そして、ドクサが発生する仕組みを「無限遡行」といいます。私はAさんが言っていたから信じる。AさんはBさんが言ったから信じる。Bさんは “みんな”が言っていたから信じる… 無限遡行とは、このように無限に根拠が先送りされ、永久に出発点に辿り着けない状況のことです。ネット上の評判など、根拠があるように見えて実は偽装されているかもしれない情報がドクサとなることもあります。これに対して、発信元が明確で学問的に実証された知のことは「エピステーメー」と呼びます。それは絶えず自己を検証し直し刷新していく知でもあります。私たちは常にそうしたエピステーメーのもとで生きていければいいのですが、実際にはそうはいかない。コンビニやスーパーでいちいち真理を求めたりできないので、社会的な通念を信じてしまいます。あるいは、風評被害を鵜呑みにして買い控えをしてしまいます。
私たちの日常の生活や経済活動は、実はものすごくもろい通念、「ドクサ」から成り立っているのです。だから、信用が何かのきっかけで崩れると、みんなが物を買わなくなります。銀行はお金を貸さない。企業は人を雇わない。バブル崩壊やリーマンショックで起きたことは基本的にこれです。1929年の大恐慌もそうです。ドクサとしての信用の崩壊です。人間がなぜこんなことを繰り返すのか、その根本を見通すには、合理的でもあり非合理的でもある人間意識を探る哲学的な目が必要です。

編集部: 4年間の学びを通じて、学生たちにどのよう力を付けてほしいとお考えですか?
サルトルは「人間は欠如の存在だ」と言っています。どんな人でも足りないところがあり、本当はこうありたいと思っている。そこで、その欠如を埋めてなりたい自分になるために、人は今の自己を乗り越えていく。これをサルトルは「脱自」と呼んでいます。そして、未来に向かって自分を投げかけることを「投企」と呼んでいます。
サルトルに言わせれば、時間は流れてきません。私たちが未来に向かって歩いていくだけです。その先に試練があって、それを越えたら颯爽とした自分が待っている。なりたかった私自身に会える。でも、残念ながら会えなかったとしても、また別の自分が生まれて、未来のどこかで私を待っている。そこに人間の自由がある。自由があるから迷い悩むし、周囲と対立もするけれど、そうしながらあなたはあなたを作っていくわけです。
人の価値は生まれつきではありません。偶然、恵まれた人間に生まれたとしても、それで価値があるわけではない。自分の存在価値は自分で作っていくものです。私は本学で教えて20年ですが、同時に母親として子育てもしてきました。そんな中でつくづく思うのは、若い人はものすごく伸びる力を秘めているということです。そして、サルトルが言うように欠如の意識があればあるほど伸びる力も大きいのです。
教育で大事なのは、それぞれが持っている欠如、それを乗り越えていこうとする力をつぶさないこと。余計な口出しをしたり、無視したり、否定したり、押さえつけたり、罰したりしては、子どもは伸びません。ぐずぐずしていたり、考えていないように見えることもありますが、実はそういう中で若い人はエネルギーをため込んでいるのです。「やるぞ!」と思ったら、突如それを全開にして突っ走ることがある。そういうタイプの学生を私は何人も目にしてきました。辛抱強く待っていてよかったな、頭ごなしに叱らなくてよかったなと。だから、教員も親も忍耐が必要です。社会のルールやマナーも上から押し付けるのではなく、なぜそうなのか自分で考え気づくよう、いざなう。そして、結果を即座に求めず、じっと待つ。いろんなタイプの学生がいて、それぞれの成長パターンがありますから、自分の伸びしろを自分で発見して、それを自分のペースで伸ばしていけるように、教員は自由で鷹揚で、かつ刺激的な環境を提供することを求められていると思います。
編集部: 社会人として活躍するために、本学部で学ぶ意義をお話しください。
皆さんが将来、企業に就職するとしたら、たとえばそこで新しい商品やサービスを開発したり、営業や取引をしたりするでしょう。そこで、自分さえ儲かればよい、会社の利益になりさえすればよいと思うか、それとも相手がなりたい自分、なりたい国になるために自分は何を提供できるだろう、と頭をひねるか。さらには、地球環境、生命、人権、尊厳、正義といった普遍的で抽象的なテーマをどこまで具体的に経済活動と結びつけて考え、自分にできることを探れるか。そこに哲学があるか、ないかの違いが出ます。本学の建学の精神の中にある「世のため、人のため」という言葉には、まさにそういう哲学があります。
本学部で経済の理論と実際の動きをしっかり学びながら、同時に人間や社会について通念を鵜呑みにせず、待てよ、と立ち止まり、自分の頭を働かせてほしいと思います。教えられたことを覚えるのは本当の勉強ではありません。自分が気づいて、疑問に思って、考えたことによって得た知は本物です。私たち教員は、そのための機会と材料を提供して、対話の相手になって、刺激を与える存在でありたい。そうすることで、学生自身が学び、成長していくのを辛抱強く見守っていきたいと思っています。

生方 淳子(UBUKATA Atsuko)教授プロフィール
●博士(哲学)/パリ第1大学(パンテオン=ソルボンヌ)大学院 哲学 現代哲学 博士課程修了
●専門/哲学、倫理学