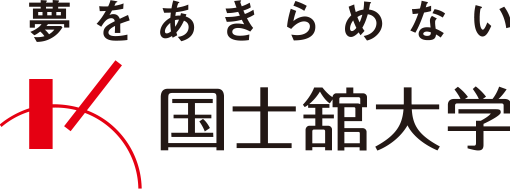【障がい学生支援室】
障がい学生支援室は、障がいのある学生(以下「当該学生」という)の修学に関する相談に応じ、他の学生と公平に教育を受ける機会を保障し必要な調整や配慮を行うために、2024年4月に本学に設置されました。実際にどんな学生を対象に、どのような支援が行われているのかについて、コーディネーターである池田先生に話をお伺いしました。
- どんな学生が支援の対象になりますか?
- 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、知的障がい、病弱・虚弱、精神障がい、発達障がい、その他心身機能障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生が対象となります。これら当該学生が他の学生と同じスタートラインに立ち公平に授業を受けることができるように、専任のコーディネーターが学部・研究科や関連部署と連係・調整を行いながら、合理的な配慮を行います。
- 障がいがあれば誰でも支援が受けられますか?
- 支援を受けるためには条件があります。第一に、当該学生自らが申請するものであるということです。障がい学生支援室の存在は本学のホームページや学習支援システムのmanabaで周知していますが、教職員や保護者の促しがあったにせよ、最終的には当該学生本人が自らの意志で申請することが前提となります。第二として、障がいを示す根拠資料の提出が申請をするために必要だということです。根拠資料としては、医師の診断書または障害者手帳のコピーや、検査所見・主治医意見書などの障がいの状況を示す書類などが挙げられます。つまり、申請をするためには、自己診断ではなく根拠となるエビデンス資料があり、なおかつ当該学生の意志により申請する、ということが条件になります。
- 具体的にはどのような支援内容になりますか?
- 先程も述べました通り、根拠資料に障がい(診断)名が示されていますので、その障がい(診断)に伴う修学上の困難さを当該学生とともに整理していきます。また、この困難さのために必要となる支援や配慮についてもまとめていきます。例えば、発達障がいと診断されている学生が、聞きながら書くというマルチタスクが困難であるため、音声録画や板書撮影の許可、資料の事前提示(配付)の依頼等の支援を申請する、といった支援内容になります。
- 申請書を提出した後は、どうなりますか?
- 学生から申請書が提出されると、大学ではその内容を吟味し、合理的配慮の対象であるか、配慮内容が適切であるかを判断します。そして、配慮が認められた場合には、当該学生には配慮内容が書かれた「決定通知書」を手渡し、担当教員には障がい(診断)名とそれに伴う困難さ、配慮内容が書かれた「依頼文」が配付されます。当該学生に渡す「決定通知書」ですが、郵送やメールではなく、当該学生本人に手渡しする形をとっています。
- なぜ郵送やメールにしないで手渡しするのですか?
- 当該学生に「決定通知書」を手渡しするときに、口頭で、「この「決定通知書」があなたに手渡された現段階で先生方には「依頼文」が配付されています、できるだけ早くmanaba等を通して先生方と連絡をとってください」と伝えています。当該学生には、「決定通知書」が手渡しされ担当教員に「依頼文」が配付されたら自動的に合理的配慮が行われるわけではありません、これが合理的配慮をスタートですよとも伝えています。また、当該学生には必ず自分から先生方にmanaba等を通して連絡をし、先生と適切な合理的配慮の内容を決定する話し合い(建設的対話)を行ってくださいと説明しています。これらのことを直接口頭で伝えるために、「決定通知書」を手渡ししています。私達は、当該学生が自らの障がい(特性)をよく理解し、他の人にそれを理解してもらえるように伝えるスキルを身につけていくことを期待しています。
- 教職員との「建設的対話」が一つの学びになるということですね?
- はい、当該学生が、「建設的対話」を通して自分の障がいや特性を他の人に伝えるスキルも高まると思います。自分自身のことをよく理解し、他の人にも理解してもらいながら充実した生活を送っていけること、そのための訓練を大学の4年間で積んで社会に出て行ってほしいと私は願っています。なかなか他の人に上手に自分の思いを伝えられないこともあるでしょう。困ったときには、いつでも支援室に来てください、可能な限り相談にのりたいと思います。
国士舘大学 障がい学生支援室
コーディネイター
池田 仁(IKEDA Hitoshi)