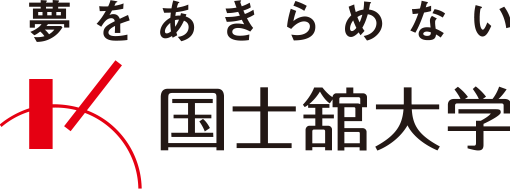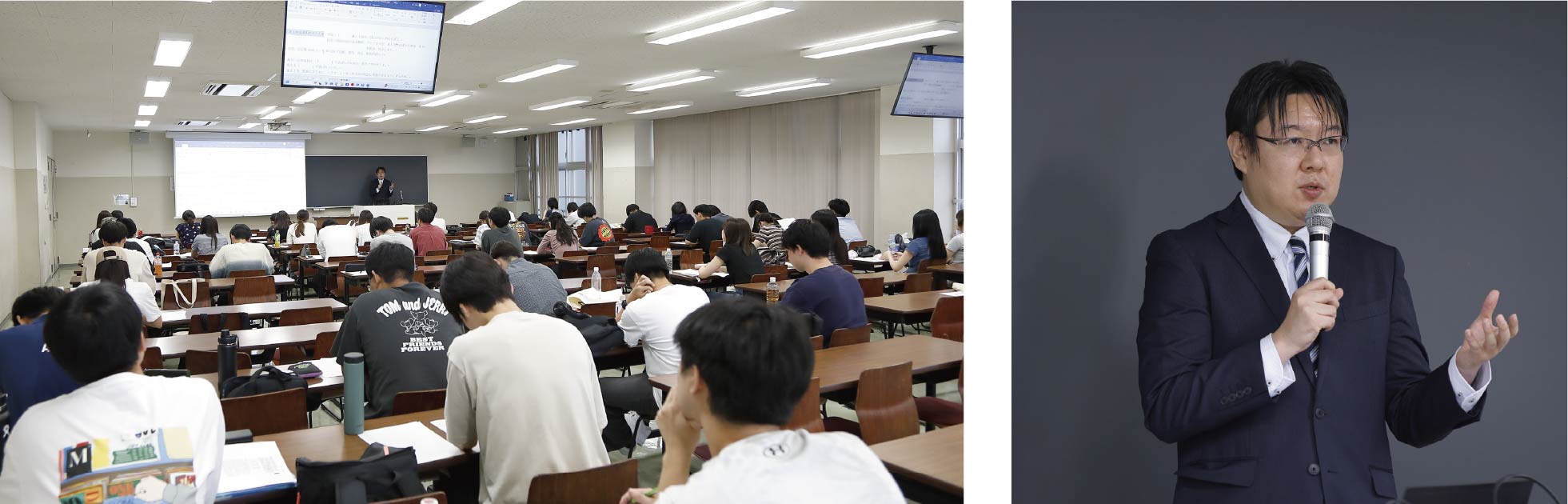国士舘大学法学部の法律学科で学んだ馬場さんは、現在、区役所の福祉関連の部署で、高齢者の総合的な生活支援に携わっています。小林正士先生のゼミで指導を受けた馬場さんは、法哲学の正解のない問いに向き合うなかで、相手を論理的に説得する術を身に付けたといいます。法の根本に立ち返り、諸問題を解決に導く法哲学の学びは、社会に出てからさまざまな形で役立ちます。法を学ぶことの大切さ、面白さを、指導教員の小林先生とともに振り返っていただきました。
法哲学の学びとは
- 編集部
- まず小林先生に伺います。先生は法学の分野で、どのような研究をされているのですか?
- 小林
- 私の専門は基礎法学で、その中でも法哲学を研究しています。特にドイツの哲学者ヘーゲルの「法哲学」を研究対象としています。
- 編集部
- 法哲学というと難しそうに聞こえますが、具体的にはどのようなものでしょうか。
- 小林
- 法の基礎に関わる探究ですね。法とは何か。正義とは何か。法や国家の本質はいかに認識されるべきか等々。こういった法の根本的な諸問題を、原理的に、基礎的に探究していきます。
- 編集部
- もう少し、わかりやすく言うと、どうなりますか?
- 小林
- そうですね。法哲学の授業でやっているのは、法と自由の関係をどう認識するかということです。たとえば、法は私たちにいろんな形で介入してきますよね。あれをしちゃいけない、これをしろと、一方で、個人の自由や自己決定が大事だという考えもあります。もし、法が個人の自由に介入するなら、そこには合理的な理由が必要です。一体それはどんな理由なのか。その理由に妥当性があるのか。こういった法律に関する基礎的なことを授業では考えていきます。
- 編集部
- 具体的な例でいうと、どうなりますでしょうか?
- 小林
- たとえば、分かりやすいのがシートベルトです。シートベルトは法律で着用が義務づけられていますよね。それは本人の身の安全を確保するためです。これはパターナリズム(父親的温情主義)の原理で正当化されます。しかし、そもそもシートベルトをするかしないかは、自己決定に委ねるべきだという考えもあります。このケースでは、パターナリズムの原理と自己決定の原理、どちらが優位なのか。優位な根拠は何か。その根拠は妥当なものなのかが議論の対象になります。
- 編集部
- 法律の条文それ自体を学ぶというより、法律とは何か、なぜ法律が必要なのかなど、そもそも論を考える学問なのですね。
- 小林
- そうです。一般的に法学というと、実定法学、即ち憲法や民法、刑法などを思い浮かべる人が多いと思います。たとえば、ある紛争の解決にどんな法律が用いられたか、そのときどのように法律を解釈すべきなのか、また裁判官はどのように解釈したのかといったことを研究していきます。これに対して基礎法学は、もっと思想や哲学に深く関係する領域です。なぜ法律が必要なのかということを、国家や社会との繋がりを意識して、根本的なところから観ていく学問です。
- 編集部
- 先生のゼミで、学生はどのようなことを学ぶのですか?
- 小林
- ゼミでは、法哲学に関するさまざまな論点を学生と議論して、何らかの答えを導き出していきます。そもそも賛否の分かれる正解のない議論なので、その都度、相手を説得する力が試されます。馬場さんの代のゼミだと、たとえば同性婚について議論しましたね。同性婚は認められるべきか否かということを。他にも臓器売買について、自分の臓器を売ることは許されるのかとか、悪法に従う道徳的義務はあるのかとか、そういった哲学的な問題について話し合います。なるべく身近な話題を取り上げて、ディスカッションしていきます。
正解のない問いに向き合う
- 編集部
- 馬場さんは、なぜ国士舘大学の法学部に入ったのですか?
- 馬場
- 自分は高校生のときに、漠然と公務員になりたいという希望がありまして、そこから考えて入るなら法学部かなと考えていました。大学にはそこまでこだわりがなくて、国士舘大学を選んだのは、場所が都内にあって、キャンパスがきれいだったからという理由です。
- 編集部
- 小林先生のゼミを選んだのはなぜですか? 法哲学というと、難しそうなイメージがあるのですが。
- 馬場
- 1年生の秋ぐらいからゼミ見学が始まって、いろんなゼミを見てまわりました。確かシラバスだったと思うのですが、小林先生のゼミでは「法とは何か」「国とは何か」ということを、そのあり方から考えるというのを読んで、興味を持ちました。
- 編集部
- で、実際にゼミを見学したのですか?
- 馬場
- はい。ちょうどコロナ禍で、ゼミはオンラインでやっていたのですが、実際にゼミ生の方が話し合っている場面を見て、面白そうだなと思いました。自分としては何か黙々と勉強するというよりは、対話を通して考えていく方が性に合っていると感じていたので、小林先生のゼミに入りました。
- 編集部
- 卒業論文は書いたのですか?
- 馬場
- はい、書きました。テーマとしては同性婚を取り上げました。
- 編集部
- どんな内容の論文ですか?
- 馬場
- 同性婚については、現状は認められていないけれど、認めることができるのではないかというテーマで書きました。実際に、当時裁判を何カ所かでやっていたので、それを調べました。
- 小林
- 確か判例もいくつか調べていたよね。
- 馬場
- はい。判例も調べましたし、あとは海外では同性婚を認めている国があるので、その国の考え方などを集めた記憶があります。
- 編集部
- 小林先生から見て、馬場さんはどんな学生さんでしたか?
- 小林
- 大人しくて、まじめな学生でしたね。裏ではどうか分からないですけど(笑)。欠席もほとんどなく、しっかり勉強していたと思います。あと、公務員試験対策の予備校に通っていることも聞いていました。コツコツやっていましたね。
- 馬場
- 授業の空き時間とかに、よく図書館に行って、問題を解いていた記憶があります。
- 小林
- ゼミの中の議論でも、馬場さんは積極的に発言されていましたね。覚えているのは2年生のときかな、国家公務員とか地方公務員とか、いろいろ目指しているという話を聞いて、そういった仕事関係の資料を集めて、馬場さんに渡した記憶があります。
- 編集部
- どんな資料ですか?
- 小林
- 裁判官の仕事とは何かとか、馬場さんは裁判所事務官にも関心を持っていたので、そういった職種の内容が分かるような資料です。参考までに読んでみたらといって、渡した記憶があります。2年生のうちにいろいろ考えて、3年生になって進路を絞っていった感じですね。
- 馬場
- その節はお世話になりました。ありがとうございます。
- 編集部
- 馬場さんが公務員試験の勉強を始めたのは、いつ頃ですか?
- 馬場
- 実際に私が動きだしたのは、大学3年生のときからです。
- 小林
- 一般の公務員志望の学生より少し遅いかもしれないけど、自分なりにいろいろ考えていたようですね。法学検定試験も、確か受けていたよね。
- 馬場
- 法学検定試験は、2年と3年のときに受けました。
- 編集部
- 法学検定試験というのは何ですか?
- 小林
- 英語に英検というのがあるじゃないですか。それと同じように、法学についての知識を問う試験です。ベーシック、スタンダード、アドバンストといった等級があります。
- 編集部
- 馬場さんは、どの級まで取ったのですか?
- 馬場
- 私はスタンダードまで取りました。
- 編集部
- 法学検定試験に合格しておくと、公務員試験に有利になるのでしょうか?
- 小林
- 公務員試験を受けた人たちからは、法学検定試験を受けておいてよかったという話をよく聞きます。なぜかというと、公務員試験にも法律の問題が出るからです。スタンダードまでやっておけば、公務員試験の法律問題はある程度カバーできると聞きます。そのへん、馬場さんはどうでしたか?
法学検定試験のススメ
- 馬場
- 公務員試験で出題される問題は、法学検定試験と似ているものが多いので、役立ちましたね。
- 小林
- 法学検定試験の勉強自体が、公務員試験の勉強になります。法学部でも、公務員志望の学生には、1、2年生のうちに受けておくことを推奨しています。
- 編集部
- 現在、馬場さんは区役所にお勤めですよね。どんな仕事をなさっているのですか?
- 馬場
- まだ勤務して1年半ぐらいなんですが、区役所の福祉関連の部署で、高齢者の総合的な生活支援に携わっています。仕事の内容は庶務に近いものですね。
- 編集部
- 実際に仕事をしてみて、大変だなと思うことはありますか?
- 馬場
- そうですね。業務量に対して人員が少なかったので、とにかく事務処理が大変でした。また、業務内容によっては区内の事業者施設を駆け巡ることもありました。
- 編集部
- 逆に、やりがいを感じたことはありますか?
- 馬場
- はい。係長が理解のある方で、新人の私にマニュアルや仕様書を触らせてくださいました。「新人の目で見て分かりにくいところがあったら修正するから」と、おっしゃってくださって。振られた仕事を淡々とこなすわけではなかったので、楽しく仕事ができました。
社会で生きる法学の学び
- 編集部
- 大学の学びで、今の仕事に役立っているなと思うことはありますか?
- 馬場
- ゼミで議論をするとき、三段論法で考えていくのですが、それが会議資料を作成したり、上司に説明をしたりするときに役立っています。話の組み立て方みたいなところは、ゼミの議論で鍛えられたことが活かせているんじゃないかと思います。
- 編集部
- こういう論理的な思考が身に付くのは、法学部の学びの特徴でしょうか?
- 小林
- そうですね。論理的に考え、説得力をもって相手に伝える。論理構成力といいますが、社会人として大切な能力の一つです。それを法学部では、法律の学びを通して養っていきます。
- 編集部
- 正解のない問いに向き合う法哲学の学びは、論理構成力が鍛えられそうですね。
- 小林
- 法哲学のゼミで大切にしているのは、根拠の「質」です。何か意見を言って相手を説得するためには、理由が必要です。ただ、理由づけることは誰でもできることで、その理由がより多くの賛同を得られるものでなければなりません。より多くの人を説得できることを目指していく。そういう訓練で、論理構成力が身に付いていくのだと思います。
- 編集部
- ところで、小林先生はなぜ法哲学の道に進もうと思われたのですか?
- 小林
- 大学時代の指導教授がヘーゲルを研究されていて、私はそこで法哲学の面白さに出会いました。法学は大きく実定法学と基礎法学に分けることができます。実定法学は、憲法や民法、刑法などに関する学問で、一般的に法学というとこちらのイメージがあります。でも、基礎法学に触れて、そうではない研究分野があることを知りました。法の基礎にある哲学とか思想とか、社会とか国家とか、それとの繋がりを強く意識して法を観ていく、その面白さを私は知ってしまったのですね。
- 編集部
- それでヘーゲルを研究されたわけですか。
- 小林
- ヘーゲルは、国家の目的は諸個人の自由や幸福にある。現代的に言えば、人権を守ることであるという趣旨のことを述べていますが、同時に国家の独立性も極めて大切であると考えていました。たとえば世界に目を向けると、ウクライナなどは国家の独立性が危ぶまれています。私たちの自由や人権の基礎には、まず他国からの不当な干渉を受けないということが大前提として求められます。国家が独立しているとはそういうことですね。
- 編集部
- ウクライナやガザで起きていることは、他人事ではないですね。
- 小林
- そうです。国家の独立性が大切だと考えたとき、今度はそれを守るのは原理的に誰なのかという問題になります。今ヨーロッパで議論されている徴兵制の是非にも話はつながっていきます。日本の現行憲法の通説では、徴兵制は意に反する苦役を禁じる18条に抵触すると考えられています。でも、一方で民主的な国家が微兵制を採用する場合、本当にこれを意に反する苦役にあたると考えてよいのかという議論もあります。法の基礎にある、個人と国家の関係をどのように認識するのかという、根本的な問題に話が進んでいきます。
- 編集部
- それが正解のない問いに向き合う醍醐味なのですね。
- 小林
- 絶対的な正解はないのですが、人々から共通了解を得られたものが、一応の正解になります。議論をして、社会的な承認を得て、広く合意を形成し、一応正解らしきものができあがる。時代や社会が変われば共通了解も変わるので、また合意形成をやり直していく。私は大学に入ったとき、法は自分を縛るもの、不自由なものというイメージを持っていました。しかし、法哲学を学ぶうちに、むしろ法は私たちの自由を守り、それを豊穣なものにするために欠かせないものであるという認識に変わりました。この法を学ぶ面白さを、ぜひ学生の皆さんに伝えていきたいと思っています。
- 編集部
- 馬場さんは、その面白さに気づいた学生の一人というわけですね。今日は興味深いお話を、ありがとうございました。
小林 正士(KOBAYASHI Masashi)
国士舘大学 法学部 法律学科 准教授
●博士(法学)/国士舘大学大学院 法学研究科 法学専攻 博士課程修了
馬場 隆太(BABA Ryuta)
2023年度 法学部卒業
足立区役所勤務
掲載情報は、2025年9月のものです。